明日はいよいよ、みやちゃん(美弥るりかさん)主演「アンナ・カレーニナ」の千秋楽ですね。
私はライブビューイングで拝見するつもりです。当然チケットは取れなかったので最初で最後の観劇(?)になります。
最近はライブビューイングを頻繁に行ってくれるようになり、チケットが簡単に取れない演目でも、映画館を通じて観られるようになったのはとってもありがたいことだと感じます。
お値段も安いですし、家から近いのもありがたい…!
そんなわけで、いまさらながら金曜日に観劇する星組さんの「霧深きエルベのほとり」の予習も兼ねて、歌劇2019年1月号を再読していました。

しかし思うのですが、こういった舞台の「予習」や「ネタバレ」はどこまですべきなのか…?というのは、いやはや、一度考えてみると結構悩ましいものではないか?と思い、今回雑記として書いてみました。
ネタバレ容認派か、否認派か
まずこういう話題になると最初に出てくるのは「ネタバレ容認派か、否認派か」というところではないでしょうか。
私はネタバレ容認派で、仮に知らない作品のネタバレをされても全く気になりませんし、これから観る作品、やるゲームのネタバレを見たとしても同様に全く気になりません。
ネタバレしない状態で観る場合は単純に「結末がどうなるのか」がワクワクできますし、仮にネタバレなどでオチを先に知っていた場合は「なぜそうなるに至ったのか」を楽しむタイプなので、全然気にならないんですね。
とはいえ否認派の方が理解できないというわけではありません。
ストーリーを新鮮に楽しむことが出来るのは最初の1回だけですし、その体験が非常に貴重であることも理解できます。
私も何度記憶を消してゲーム「逆転裁判」シリーズをやれないだろうか…と考えたことでしょうか。
しかしながら、最近ではTwitterなのでネタバレを意図せずに見てしまう機会も増えているであろう昨今、ネタバレ否認派の方は「自衛」を余儀なくされているな…と感じます。
「歌劇」の座談会は結構ネタバレ?
といった前提はさておきまして、話を宝塚歌劇に戻しましょう。
宝塚歌劇の場合、ありがたいことに公演が始まるまで~終わるまでのフォローが非常に手厚くなっております。
具体的には、その公演が始まる月に発売される「歌劇」誌面において「座談会」が掲載され、その作品について演出家とメインキャストがそれぞれの役やストーリー展開などについて語ってくれています。
今回で言えば、望海風斗さんが表紙を飾った「歌劇 2019年1月号」が該当します。
今月号に限らないのですが、歌劇の座談会は毎回、結構ネタバレしてないか?と感じることがあります。
ネタバレ容認派・否認派とざっくりと2つにわけましたが、その中でも細分化されているわけで、過激否認派(いるのかしりませんが)でしたら、この内容でもかなりネタバレになってしまうのでは…と思うことはあります。
というのも、舞台上で出てこない裏の心やどうやった心持ちで演じているかなどを座談会でしっかりと語ってくれるため、舞台をより深く知るには非常にありがたい資料でありながらも、ネタバレというゾーンに片足突っ込んでいるのではないか…とも思ってしまうわけです。
私は今回、「アンナ・カレーニナ」も「霧深きエルベのほとり」もどちらも1回しか観劇(ビューイング)することがかなわないため、出来るだけ1回の観劇から多くの情報を受け取りたいな、と思っています。
そのため、座談会やNOW ON STAGEといったスカステの関連番組もチェックしているのですが、実際否認派の方からしたらどうなんだろう…?と考えることはあります。
再演ものはネタバレしてもいいのか否か
さらに、今回観る2作品はどちらも「再演もの」です。
素晴らしい演目という財産がある宝塚にとって、再演することは珍しいことではありません。
ただ再演するというだけではなく、現在の時勢に合わせて…など、演出家の方々のスパイスが入るため、「懐かしさがありながらも新鮮」であったり、「ストーリー自体は一緒だけど細かく演出が違う」という楽しみ方が出来ます。
再演ということは、「すでにネタがわかっている演目」だと言うことです。
となると、再演ものはネタバレの対象となっても別におかしくないな、というのが容認派の私の考え方でもあります。
例えば去年月組で上演されました「エリザベート」。
それぞれの演者に対する感想などはありましたが、そこでストーリーのネタバレに配慮しているか?と言われるとどうなのかな…とも思います。
わざわざネタバレしているというわけではなく、知っていることが前提で語られている、とでも言いましょうか。
世の中には様々な方がいて、私が知っている方ですと「いくら放映されたのが10年以上前であっても、これから観るかもしれないもののネタバレも許さん」というタイプの方がいらっしゃいました。
そういうタイプの方にとっては、結構宝塚は鬼門なのではないか…と思ってしまいますね。
初見でのわかりやすさも注目したい部分
私は出来るだけ情報を入れて観劇などをするタイプではあるものの、「初見でのわかりやすさ」も重要だと思っています。
自分は宝塚、特に贔屓の明日海りおさんがいる花組の演目は複数回観るのが前提となっていますが、「舞台は1回だけ観られればよい」という方も大勢いらっしゃると思います。
お芝居の場合であれば、その1回でお話がわからなければ作品としてあまりいいものではない、と私は思っています。
1回で話がわかり、2回目、3回目とみるとまた新たな発見がある…というのがいい作品だと思っているので、予習をしっかりしてしまうと「ある程度わかった状態」で観てしまうので、初見のわかりやすさが判別し辛いというデメリットも抱えていると考えています。
もちろん舞台の見方は人それぞれですので、どの方法がベストというのは言えないのですが…。
私個人では、
- 観劇回数が少ない(1回~2回)→出来るだけ予習をして話の筋を叩き込んで観る
- 観劇回数が多い(3回以上)→予習せず初見からを楽しむ
といった形にしています。皆さんはどうでしょうか?
■スポンサードリンク■
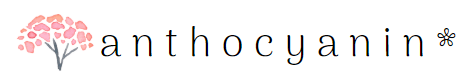




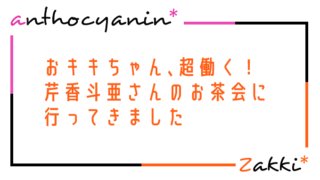
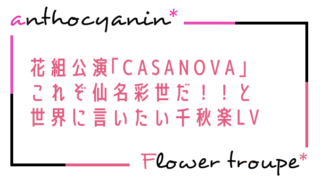
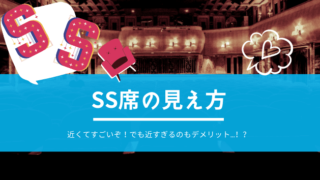
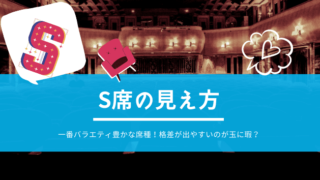

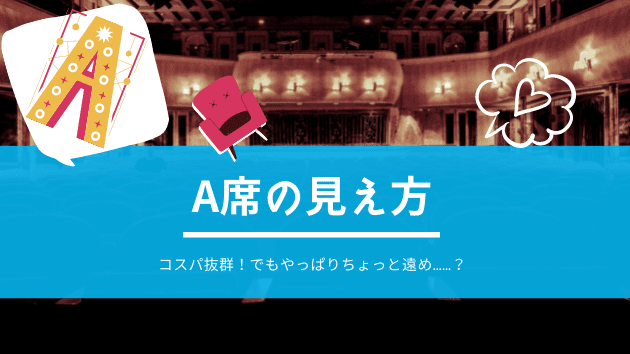
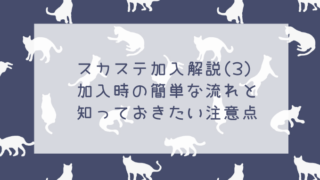
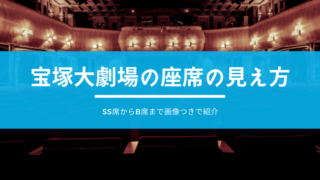



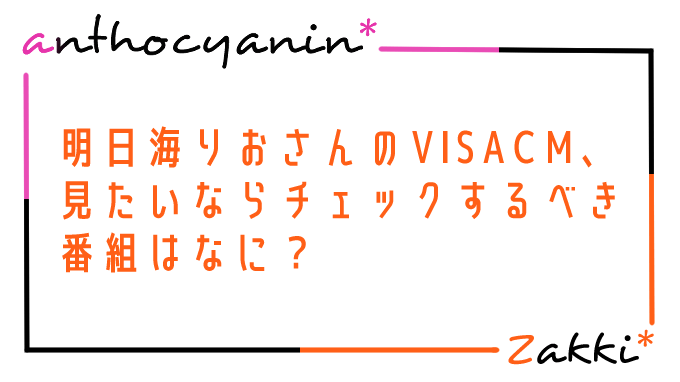
コメント