月組、美弥るりかさん主演のバウホール公演「アンナ・カレーニナ」の千秋楽ライブビューイングに行ってきました。

正直、ロシア文学ということで「絶対これ内容暗いやん…」と思っていたのですが、いい意味で裏切られ、非常に楽しく観劇してまいりました。
ハッピーエンドとは言えない内容ですが、非常に美しく、そして心に痛みを伴う作品になっていて、観終わったあともじんわりとくるような、そんな優しさもある作品でした。
原作は読んでいないのですが、演出家の植田景子先生の手腕もあるのだろうなと勝手に思っています。
また、この作品は再演となりますが、観たのは今回の月組バージョンのみなので、比較なども出来ません。よって、ただシンプルに長文感想を書きなぐる(毎度のことですが)だけとなります。
様々な愛の形があり、考えさせられるもの
この作品は、タイトルロールであるアンナ(海乃美月さん)と ヴィロンスキー(美弥るりかさん)の命を燃やすような激しい愛を軸に、アンナの夫であるカレーニン(月城かなとさん)の「相手を赦す、包む愛」や、アンナの兄であるスティーバ(光月るうさん)の浮気を楽しみながらも、結局は妻の元へ戻る「男の甲斐性的な愛」、純朴な田舎の貴族の青年コンスタンチン(夢奈瑠音さん)の、キティ(きよら羽龍さん)への「純粋な(尽くす)愛」といった、非常に様々な愛の形が描かれます。
作中ではどの愛が一番!というものではなく、それぞれの立場や自分の住む世界などに合わせて、自分なりの愛の形、愛し方などを見つけるべきなのだ…といった感じになっております(もちろん個人の感想です)。
アンナとヴィロンスキーの二人の場合は、これまで本当の愛を知らずに生きてきた二人が、出会ったゆえにお互いの全てを捨ててまでも一緒にいようとしますが、それがまた苦悩をうみ、最後は…という、非常にシンプルな展開になっていて、スムーズにお話が頭の中に入りました。
いくら強く愛し合ったとしても、その結末が決して幸せになるとは限らないという、美しくも痛みを伴うお話になっていて、その儚さがまた憧れさせるといいますか、「一生に一度はこんな恋をしてみたいな…」と思わせてくれるのかもしれません。
様々な人を傷つけても止められない愛の強さ
このお話の中心である、アンナとヴィロンスキーのお互いを求め続ける愛は、いろんな人を傷つけ、巻き込んでいきます。
アンナの家族であるカレーニンと息子のセリョージャ(蘭世惠翔さん)、ヴィロンスキーの家柄など、社交界での噂になることで、最終的にアンナは外へも生きづらい状態にまで追い込まれます。
それでも愛している、破滅しか待っていなくても二人でいるしかない…という愛の強さは、不貞という関係ながらもどこかピュアに見えるのが不思議ですね。
いわゆる「社交界の火遊び」であれば、このようなことにはなりません。二人は不器用で、本当の恋をしたことがなかったからこそ、深く落ちていってしまったとも言えそうです。
入りは「仮面のロマネスク」のヴァルモン子爵とトゥールベル夫人の関係を思い起こさせますが、最終的には「金色の砂漠」のイスファンディアールとタルハーミネのような感じでしょうか。
ヴィロンスキーの旧友、セルプホフスコイ(英かおとさん)が、ラストで「彼(ヴィロンスキー)は全て失った。私は地位も名誉も手に入れた。なのに、棍棒で殴られた時のように敗北感を感じている。彼は私達が決して手に入れられなかったものを手に入れたのだ」と語りますが、周りを巻き込みまくりで傷つけたとしても、最後は破滅という結末を迎えてしまったとしても、それでもそれ以上に輝かしいものを手に入れたように見える…というのは、人はやはり愛なくしては生きてはいけないのだろうと思わせるセリフだな、と感じますね。
このセリフが本当に美しくて、これがあるからこそこの物語が成立するとまで言えると思います。
アンナ・カレーニナというお話は、様々な愛の形を描いていますが、それぞれを肯定するわけでも否定するわけでもなく、ただ、その時の社会には迎合されなかったであろうヴィロンスキーとアンナの愛は、光として私達の心に何かを落としたのだな、と感じられる作品だと感じました。
いろんな人に対して「わかる…」と言いたくなる
このお話の個人的に面白いところは、誰にも共感出来る、という部分でした。
お芝居に限らず、漫画やゲーム、アニメなど、もちろん内容にもよりますが、一人や二人は共感出来ない人間が出てくるものなのですが、この作品はそれがありませんでした。
アンナは貞淑で賢い女性なのだと思いますが、中に強い想いを秘めており、その想いのままに走った女性です。
でも(現代日本で不貞はいけませんけども)彼女のような恋をしてみたい、と思うことは一度はあるのではないでしょうか。
ヴィロンスキーもアンナと出会って彼女一直線になってしまいますが、あのように愛されたら嬉しいと感じるでしょうし、やはりそれほどの恋をしてみたいというふんわりとした希望を持った経験はありますよね。
カレーニンはこのお話では一番の苦労人といいますか、ババ引いてるポジションですが、世間体のためにきちんとして欲しいとアンナに言う場面など、男性・夫としては冷たい言い分かもしれませんが気持ちは理解できます。
このように、どこか自分と重ねられる、自分もそう思ってみたい、思ったことがある…といった、どこかこれまで自分の中に引っかかっているものがそれぞれの役に散らばっているのかもしれないな、と感じました。
破滅からの再生が繰り返される?
突然ですが、このお話は破滅→再生→破滅と、破滅と再生の繰り返しが多いように感じました。
小さなものですと、スティーバの浮気が原因で、妻ドリィ(楓ゆきさん)が離婚する気満々でしたが、そこからの復縁。破滅…というには仰々しいですが、マイナスから復帰していることは間違いないと言えるでしょう。
コンスタンチンとキティの関係もそうだと言えます。キティは最初彼の求婚を断りますが、その後ヴィロンスキーに振られたことにより、改めて彼のことを考え、彼の愛を感じ、最終的には結ばれます。
アンナとカレーニンもそうなんじゃないかと私は思っています。
二人の関係は変化こそなく平和ではありましたが、ヴィロンスキーが現れることで夫婦間の隙間が見え、夫婦関係としては破綻してしまいます。
しかしその後和解し、お互いの気持ちこそ違いますが、関係自体は多少修復されたと言ってもいいのではないでしょうか。
そしてアンナとヴィロンスキー。
アンナがヴィロンスキーの子、アーニャを産んだ後も熱が下がらず病床に臥せってしまいます。
うわ言のようにカレーニンに許しを請いたいと言うアンナに対し、ヴィロンスキーは「自分は愛しか与えることが出来ず、(病気から)救うことは出来ない、こんな風にしてしまったのは自分のせいだ」と自殺しようとします。
正直ここで死んでしまうのかなるほど…と思ったのですが、まさか生きているとは。
アンナは死んだと思っていた彼のもとに、彼女が奇跡的に快復したという知らせが。どっちも死の淵から帰ってきてるの強ない!?
ここで一度関係を終わらせようとお互い思っていたものの、再会したらその気持は止められず…。
その後、アンナが死んでしまうまでその関係は続きます。
物語だからこそ見てられますが、自分がその立場になったら恐ろしくてたまりません。絶対にメンタルやられます。
イタリアで死んだのかと…
二人が死の淵から戻ってきた後再会し、絶対に離れられないと改めて感じた二人は以前話していたイタリアへと飛びます。
突然そこから楽しく平和な二人が描かれてしまうため、「もう死んだんかな…もしくは誰かの妄想かな…それともこのシーンのあと二人で死ぬんかな…」と思うレベルでした。
どっちも死ななかった。むしろロシアにも戻ってきた。
美しいラスト
私はロシア文学に偏見があるため「ラストは悲劇だろうなあ」と覚悟が出来ていたのもあり、大体最初の方からオチはなんとなく推察できていたのですが、美しいラストだなと思いました。
セルプホフスコイのセリフが刺さったというのもありますが、アンナがああなってしまったのはなるべくしてだと思いましたし(モルヒネまで使っていますし…)、そこでヴィロンスキーが戦場に行くという選択を取ってはいるものの、生きることを捨てなかったことも素敵だなと思います。
超余談
※お話の余韻を崩すような話題なのでご注意ください※
音楽もとても素晴らしいものだったのですが、(アンナが列車の中でゲーテを読んでいるシーンで歌った曲、どこか不協和音のように聴こえてゾクリとしました。これからの破滅を予感させるような感じで…)劇中で2回ほど、チャイコフスキー作曲の「弦楽セレナーデ」が流れました。
インパクトが強く、強さの中に哀しみもたたえたような曲なのですが、私は某CMを思い出してしまいまして…。
真剣なシーンなのに、この音楽がかかるとちょっと笑ってしまいそうになってしまいました…。CMという媒体の強さに改めて気付かされました。
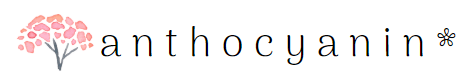









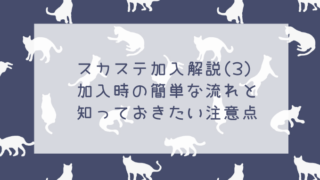







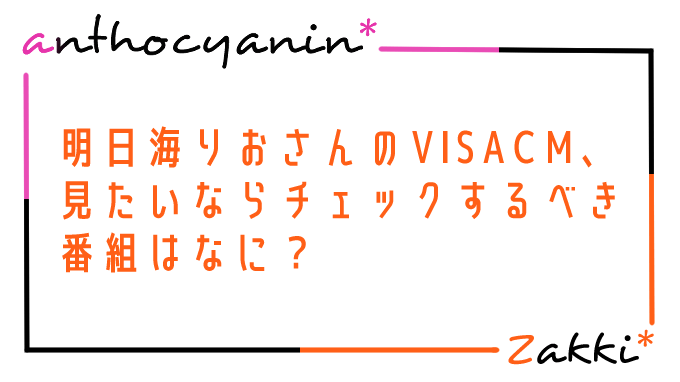

コメント